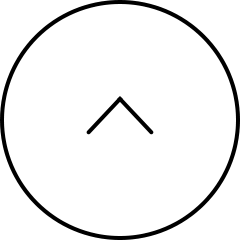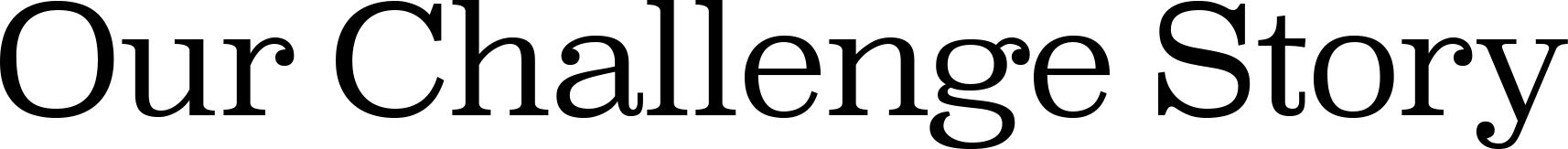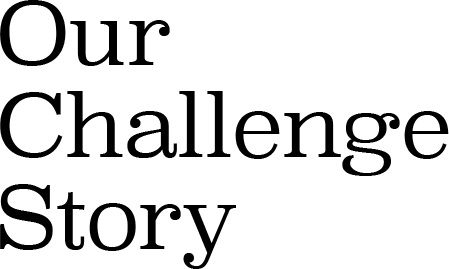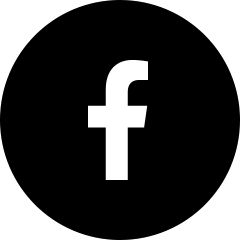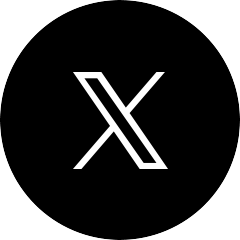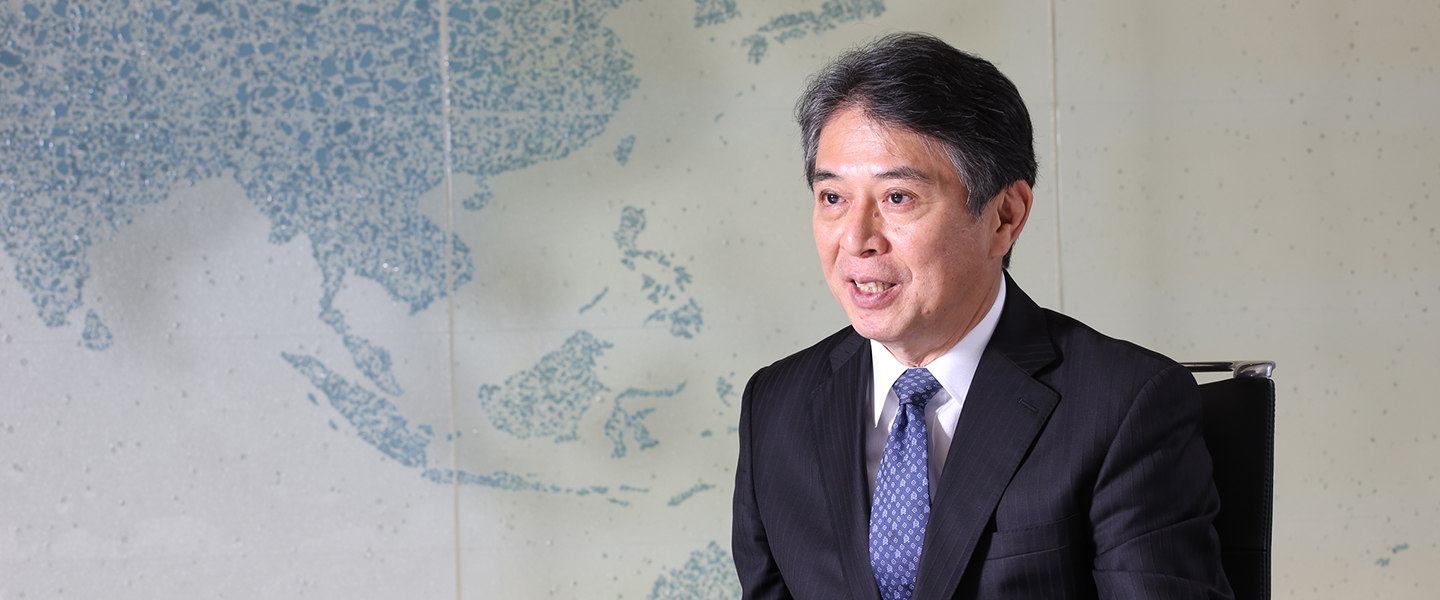

長期的な視点と信頼が生み出す新事業 AGCが培うDNAと未来への挑戦
- #経営戦略
- #スピリット
「両利きの経営」を体現する企業と評価されたAGC。その歴史は常に新分野への挑戦に彩られてきた。次世代の成長分野を見極め、10年、20年と長期にわたる素材開発を経て市場での圧倒的な優位性を確立する。将来事業の見極めや開発ポリシーなどについて、代表取締役 兼 社長執行役員CEOの平井良典氏に聞いた。
Profile

平井 良典
AGC株式会社 代表取締役 兼 社長執行役員CEO
1987年東京大学大学院工学系研究科博士。2008年に液晶パネル製造の子会社オプトレックス(当時)の副社長、2011年にAGCの事業開拓室長。2016年CTOを経て2021年1月から現職。京都大学の客員教授として年に数回教壇に立つ。学生時代には物理学者を志していた。福井県出身
米スタンフォード大学経営大学院教授のチャールズ・A・オライリー氏が提唱する既存事業の深化と新規事業の探索を両立する「両利きの経営」。AGCは日本企業としてこれを体現する企業と認められ、同大学院のケーススタディーで紹介された。「両利きの経営を意識してやってきたわけではないが、創業以来、新事業に挑み続けてきたのは事実」。同社 代表取締役 兼 社長執行役員CEOの平井良典氏はそう語る。

AGC株式会社 代表取締役 兼 社長執行役員CEO 平井 良典 氏
1907年に創業。その2年後に日本で初めて建築用ガラスの量産を開始した。第1次世界大戦時には一部の原料や、窯のレンガ材が輸入できなくなり、内製化に挑んだ。「これが現在の化学品やセラミックスの事業につながっている」(平井氏)。
高度経済成長期には、自動車とテレビの市場が急成長。同社はいち早く自動車用窓ガラスやブラウン管用ガラスの生産を手掛けた。新たな成長分野に素材を通じて貢献する精神は同社の根幹を成す。
21世紀に入ると、大黒柱だった旧来のガラス事業が失速し始める。入れ替わるように、液晶ディスプレイ用ガラス基板が急成長し、業績は一気に拡大したが、その裏で経営陣は危機感を抱いていたという。
「数年で失速する可能性があると伝えた」。当時、社長だった石村和彦氏に呼び出された平井氏が、ディスプレイ事業の先行きについて聞かれたときのことをそう語る。液晶ディスプレイ用ガラス基板の成功で、同社が史上最高益を記録するのは2010年。その1年前のことだ。
業績は絶好調。皆がディスプレイ基板に熱くなっていた時期に、なぜそんなことを聞くのか。平井氏は自身が社長となった今ではその意図が痛いほど分かる。一部の方からは「ディスプレイ1本足打法」と呼ばれるほど、当時の同社はこの事業に頼りきっていた。
「素材産業は研究開発の着手から事業化までに10~20年かかるのは当たり前。だからこそ、1つの事業がピークを迎える前に、次のことを考え続ける。常に複数の分野へ根を張る。これが当社のDNAなのです」(平井氏)。米国の大学教授に「両利きの経営」の体現者と評価される、その根幹がここにある。数年後、ディスプレイ用ガラス基板事業は平井氏の予言通りとなった。
「ディスプレイ用ガラスに代わり収益の柱となる事業を育ててくれ」。当時の社長にそう託された平井氏は2011年に新規事業創出のために設立された事業開拓室(当時)の初代室長に就任し、2016年のCTO就任後もずっと責任者の立場で新事業創出に関わり続けてきた。そしてAGCは2016年に前CEOの島村琢哉氏のもと長期経営戦略「2025年のありたい姿」を発表。建築用・自動車用ガラスや化学品などの既存事業をコア事業と位置づけ、そこで確固たる収益基盤を築くとともに、モビリティ・エレクトロニクス・ライフサイエンスの新事業を今後の収益拡大を担う戦略事業と位置づけ、そこに経営資源を積極投入することを宣言した。
戦略事業の一例を紹介すると、モビリティでは自動車のインパネに使われる車載用化学強化ガラス、エレクトロニクスではEUV(極端紫外線)露光用マスクブランクス、ライフサイエンスでは医薬品の製法開発から製造までのプロセスを受託するCDMO事業。その多くは平井氏が過去10年にわたり関わってきたものだ。
積極的に事業ポートフォリオを拡大してきた同社だが、成長分野なら何でも手を出すわけではない。新分野の開拓にはポリシーがある。
第1のポリシーは、「飛び地はやらない」だ。従来の技術や経験を生かせない分野には進出しない。好調なライフサイエンス事業は、同社が持っていたフッ素系の合成化学からスタートした。半導体の分野も、ガラス基板の技術や経験を派生させる形で合成石英や研磨剤などへ広げている。
第2のポリシーは、「B to B事業へのこだわり」だ。「過去にB to C事業に手を出したこともあったが、うまくいかなかった。やはり社風に合わない」(平井氏)と笑う。AGCは創業以来、その中核を素材開発・生産に置いてきた。医薬品の素材開発や生産は受託するが、薬品メーカーにはならない。この姿勢を貫く。
裏を返せば、AGCは顧客の競合にはなりにくいということだ。だからこそ、顧客は安心して新製品を一緒に開発できる。モデルチェンジや新製品を企画するときは必ず最初にAGCに声がかかる。こうした信頼関係を構築できることが同社の財産だ。
第3のポリシーは、「きちんともうかること」だ。マクロトレンドから見て確かな市場性があるか、技術的な差異化によってAGCが圧倒的な強さを発揮できるかなどを見る。
同時に、その分野で圧倒的に強い顧客と組めるかどうかも重要な指標だ。「短期的な収益より、継続的な収益を重んじている。それには当社の技術力とお客様との関係性、この2つが非常に重要な要素になる」(平井氏)。

例えば、EUV露光用マスクブランクスの事業は、開発から量産に至るまで約20年かかった。スタートから10年がたっても、量産につながる気配は全くなかったという。それでも途中でやめなかった理由は、「市場が立ち上がれば大きな産業になると将来を見通した上で、得意とするガラス素材と加工の技術が不可欠と分析していたから」(平井氏)。
また、バイオ事業も苦節20年の末にようやく事業化した。バイオに関する技術開発については、そのとき芽が出ていなくても歴代のCTOが継続を決めてきたという。「挑戦こそが当社のDNAであることは全員が理解し、そのポリシーは明確。専門分野の違うCTOが引き継いでも、論理的に考えれば同じ答えに行き着く」(平井氏)。
新事業の開発は本社の事業開拓室(当時)が行い、事業化のタイミングで関連する事業部門に引き渡す。そこは人材育成の場として、30代の若手人材を必ず参加させている。
新事業の開発を事業部門から切り離している理由は、「事業ポートフォリオを変えるような大きな新事業は、既存事業を運営している組織から生まれにくいから」(平井氏)だ。
画期的な新技術は、時に既存の製品や技術を無意味化してしまうことがある。つまり、既存事業を支えている部門から見ると、新規事業への投資は既存事業の足を引っ張り、自己否定につながることがある。そこで、新規事業は本社の管轄としてきた。
同時に、異分野の知恵やノウハウを積極的に取り入れる。近年、大学との緊密な連携を複数スタートさせたほか、2021年6月にオープンしたAGC横浜テクニカルセンターにも、外部の大学や研究機関と協創できるエリアを設けた。
人材面では、キャリア採用(中途採用)を積極的に実施し、拡大する事業ポートフォリオに適した異分野の専門性を持つ人材を集めている。また、この10年間に海外でかなりの数のM&A(合併・買収)を実施した。M&Aの際に気を付けるポイントは、買収を目的化していないことだ。企業を買収した後、AGCグループにどう統合すれば効果を最大化できるか。周到に計算してM&Aに臨んでいる。
SDGsに対する注目が高まる中、素材メーカーを取り巻く環境は厳しさを増している。中でも2050年のカーボンニュートラルに向けた戦略が企業にとって重要な課題だ。同社は2014年に「2020年に自社が排出する温室効果ガスの6倍を自社の製品で削減する」という目標を立て、断熱ガラスによる冷暖房エネルギーの削減などでおおむね達成した。
一方で、自社の生産工程での脱炭素も重要なテーマになっている。あらゆる素材は原料にエネルギーを加えることで生まれる。原理的にエネルギーの使用は避けられない。
例えば、ガラス原料を溶かすには1600℃程度まで加熱する必要がある。同社は燃料を石油から天然ガスに替えるなどして環境負荷を低減したが、さらなる低減には、熱源を電気に切り替えるなどの技術開発が不可欠になる。AGCは今年発表した中期経営計画の中で、2050年までにカーボン・ネットゼロを実現するという目標を設定した。
「1つの素材を世に出すのに10~20年はかかってしまう。素材メーカーの経営には、長期的なビジョンと継続性が欠かせない」(平井氏)。持続可能な社会の実現へ、いかに貢献するか。重要なのは、大きなビジョンで挑むこと。平井氏はそう将来と向き合い続けている。
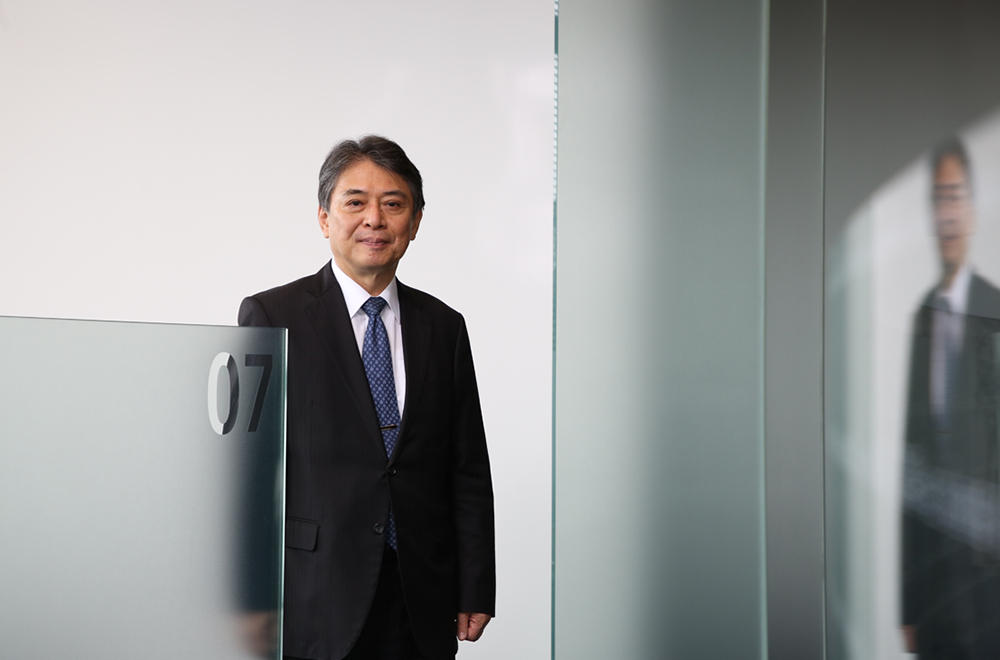
日経ビジネス電子版 Special 掲載記事